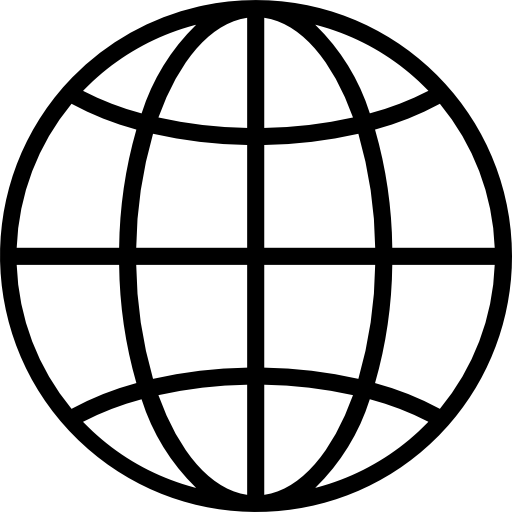I. はじめに:Will Groupにおけるデジタルエコシステム
現代の企業において最も重要な資産は、物理的なオフィスではなく、チームがつながり、協働し、創造する「デジタルエコシステム」です。私たちの場合日々の業務を支えているのは、Microsoft 365 Business Premiumです。この統合的なシステムは、多様な環境で働く従業員が場所を問わずシームレスかつ安全に業務を遂行することを可能にしています。日々のコミュニケーションの中心はMicrosoft Teams上で行われており、簡単な確認から定期的な進捗報告、オンライン会議まで、あらゆる場面で活用されています。SharePointとOneDriveは私たちの共有ワークスペースとして機能し、チームメンバーはそれぞれの場所からリアルタイムで情報に関する共同作業を行えます。さらに、Power BIやMicrosoft Formsといった分析・ビジネスアプリケーションを活用することで、データの可視化やワークフロープロセスの構築を効率的に進めることができます。
また、BullhornやLinkedInといったCRM(顧客関係管理)プラットフォーム、そしてAutomateやMessagingなどの関連アプリケーションは、人材紹介プロセスにおいて不可欠なツールとなっています。これらのツールにより、当社のコンサルタントは広範な専門家人材のネットワークとつながり、候補者の斡旋を効率化し、優秀な人材とより効果的に関わることが可能になっています。
しかし、この効率性と相互接続性の高まりの中で、私たちは自問しなければなりません。テクノロジーは、真の人間的なつながりを育み、チームの結束力を高め、企業文化を豊かにしているのでしょうか?逆に、コミュニケーションやチームワーク不足に陥ってないでしょうか?
II. 中核となる課題:本質的な対話 vs デジタルな利便性
チームメンバーは、個々の業務の中でテキストメッセージやEメールを交換するだけに留まっていないでしょうか? より深い協業や、オープンなアイデア交換を可能にする、本質的な対話に時間をかけているでしょうか?真の成功は、テクノロジーを単に業務効率化の手段にするだけでなく、個人がそれぞれ課題に取り組みつつも、組織が一つのチームとして協働する文化を築くために活用すしていくことです。
メッセージツールの利便性が本質的な会話に取って代わってしまうことがあまりにも多いのが現状です。チームメンバーは、チャット上でテキストやコメントを交換するのみで、イノベーションを刺激し、誤解を解消し、信頼を築くような対面での対話を怠るかもしれません。これは決して小さな問題ではありません。Grammarly社のレポート「2024 State of Business Communication」によれば、米国内の企業において、職場のミスコミュニケーションが引き起こした損失は、前年、推定1.2兆ドルに上ると報告されています。デジタルな利便性は、かつて会議室やコーヒーブレイクで生まれていたような、より深い人間関係や自発的なアイデア共有の機会を少しずつ蝕んでいる可能性があるのです。
これがなぜ重要なのかというと、ハイパフォーマンスなチームは書類上だけで協業しているわけではないからです。彼らは対話を通して信頼関係を築き、互いに切磋琢磨し、そして一緒により大きな全体像を見ています。だからこそチームリーダーは、重要な議論や意思決定を行う際には対面またはビデオミーティングで交流することを奨励します。これは、部門横断的なチームが定期的に集い、アイデアを共有する機会を創出し、コミュニケーションの「速さ」だけでなく「質」を重視することを意味します。
私たちは、テクノロジーを「代替物」としてではなく、あくまで「ツール」として活用しなければなりません。共感、協業、メンターシップ、そして信頼といった、パフォーマンスを真に促進する人間的要素の代替物ではありません。なぜなら、最終的に成功する組織を築くのは、テクノロジーだけでは不可能だからです。最終的な成功を築くのは「人」です。人々が共に働き、互いに耳を傾け、一つのチームとして前進することによって、組織は築かれるのです。
III. 諸刃の剣:グローバルな接続性 vs. 表面的な関係性
現代の職場テクノロジーは、通知音、複数のチャット、連続するバーチャル会議など、絶え間ないデジタルのリズムを生み出します。Will Groupの多様なブランドポートフォリオにおいて、私たちは地域、職務、タイムゾーンを越えてチームをつなぐ、豊かなコミュニケーションツールシステムを活用しています。このグローバルな接続性により、リアルタイムの協業が実現し、意思決定は加速され、事業運営の機敏性が保たれています。
しかし、私たちはかつてないほどつながっている一方で、これらの交流の質が時として表面的になり、短いチャットが深い対話に取って代わられたり、戦略的な全体像を欠いたまま意思決定が下されたりすることがあります。この効率性は、時に「深さ」を犠牲にしているのです。ほとんどの会話がデジタルで行われるため、自発的な声かけや偶然の会話が少なくなりました。これにより、業務報告は議論よりも完了報告に重点が置かれ、表面的なものに感じられがちです。長期的には、これが意図せずして戦略的な連携や組織の成果を弱めてしまう可能性があります。
複数のチャネルが絶えず情報を発信する中で、チームメンバーはデジタル疲れや情報過多に直面することが増えています。近年の調査はこの問題の深刻さを浮き彫りにしており、Slingshot社の「2024年デジタルワークトレンドレポート」では、従業員の34%がデジタルデバイスに費やす時間に圧倒されていると感じており、この割合はマネージャー層では39%にまで上昇します。これは心身の健康に影響を与えるだけでなく、集中力、創造性、そして深く思考する能力を低下させる可能性があります。生産性への代償は計り知れません。カリフォルニア大学アーバイン校の研究によれば、デジタル作業中断の後に完全に集中力を取り戻すには23分以上かかることもあり、これは私たちの認知リソースに重い負荷をかけています。だからこそ私たちは、意識的に「アナログな時間」を設けることを、これまで以上に奨励しなければなりません。画面を使わない議論やブレインストーミング、Eメールやチャットに中断されない深い思考のための時間確保などは、イノベーションを育み、チームが単なる速さだけでなく明確なビジョンを持って前進するために不可欠な戦術です。
テクノロジーのリーダーである私自身でさえ、スクリーンから離れる瞬間に真の価値があると感じています。紙にさっとスケッチしたり、オフラインで議論したりすることで、ツールでは得られない明確さが生まれることがよくあります。このようなアナログな瞬間に加えて意図的に設計されたデジタルが組み合わさることで、真のイノベーションが生まれるのです。
IV. 文化の潮流:Will Groupのグローバルかつ多文化な環境におけるテクノロジー
職場へのAIやデジタルツール導入の流れは非常に強くなってきています。PwCの2025年のレポートでは、AIの影響を最も受ける業界は、最も影響を受けない業界よりも大幅に高い生産性の伸びを示していると述べています。私たちのようなグローバルグループにとって、この力を活用していくことは必須です。私たちのようなグローバルグループにとって、この力を活用していくことは必須です。
さらに、テクノロジーの使われ方は文化によって異なります。私の職務において、グローバルチームのコミュニケーション方法には興味深い違いがあることに気づきました。ある地域の同僚にはTeamsでの短く非公式的なメッセージで十分かもしれませんが、日本のパートナーは、重要な依頼に対して、より丁寧で形式に則ったEメールでのコミュニケーションを希望する傾向にあります。これを理解することは単なるエチケットの問題ではなく、プロジェクトの効率性や関係構築に直接影響します。Notta社の2024年のレポートで、若い世代の労働者は年長の同僚に比べて対面での会話を好まない傾向が示されており、この世代間の変化は、多文化・多世代チームを管理するリーダーにとって、さらなる複雑さをもたらしています。
だからこそ、リーダーは明確なコミュニケーションの規範を設定するために積極的に行動しなければなりません。Gallup社の報告によると、自社が従業員のウェルビーイングを真に気に掛けていると感じている従業員はわずか23%に過ぎず、テクノロジーをきちんと活用して文化的なギャップを埋めることはもはや必要不可欠な要素であり、エンゲージメントと人材定着のための極めて重要な戦略なのです。その第一歩は、これらの違いを認識し、チームに単なるツールではなく、国境を越えた効果的な協業のためのフレームワークを提供することです。
V. デジタルでつながるWill Groupブランド全体での信頼の構築
Will Groupのようなグローバル組織では、多くのチーム、さらにはブランド企業全体が日常的に顔を合わせることがないため、信頼、心理的安全性、そして帰属意識を育むことは独自の課題を伴います。これは単なる感覚的な問題ではありません。Perceptyx社が2,000万人以上の従業員を対象とした2024年のレポートでは、労働者の10人中4人以上が孤独を経験しており、これが生産性と離職率に重大な影響を与えていることが明らかになりました。テクノロジーはシームレスな協業を可能にしますが、交流の多くがスクリーンの裏に隠れているため、人間関係がタスク志向の活動に限定されてしまうリスクがあります。特に分散したチームにおける本質的なコミュニケーションには、巧みに作られたテキストやEメール、レポートだけでは足りません。人間的なつながりのための信頼関係の構築、たまの雑談、時にはユーモアも必要です。
私たちのチームメンバーネットワークでは、透明性の高いリーダーシップ・コミュニケーションやインサイトの提供、生産性とウェルビーイング向上のためのセミナー開催、そして貢献、情熱、献身によって周囲を「WOW!」させた受賞メンバーの成功を称えることを通じて、信頼を築く瞬間を常にサポートしています。
そして、誰もがその役割を担うことができます。例えば、オンライン会議でカメラをオンにする、Teamsのチャネルで成功を祝う、タスク以外の「元気?」という声かけに時間をかけるなど、些細でも意味のあるデジタルな習慣を実践することです。これらの瞬間は、シンプルながらもリモート中心の環境において帰属意識と信頼関係を育む助けとなります。
同様に重要なこととして、私たちのテクノロジーおよびセキュリティポリシーは、その信頼を支える基礎的な役割を果たしています。当社のITセキュリティポリシーはNISTサイバーセキュリティフレームワークに基づいており、規制遵守だけでなく、情報の保護方法やアクセス管理方法の明確性と公平性を保証しています。世界的に認められた基準に準拠することで、私たちはチームに、デジルの職場環境が安全で、安定しており、きちんと管理されているという信頼感を提供します。この公平で透明性の高いセキュリティ環境を創出することで、心理的安全性と信頼が築かれる安定した基盤を提供しているのです。
VI. テックリーダーのビジョン:Will Groupとその未来のための架け橋としてのテクノロジー
意図的なテクノロジーの導入とは、単に「どのツールがこの問題を解決するか?」と問うだけでなく、「このツールは、私たちの働き方、考え方、そしてつながり方をどのように形成するのか?」と問うことです。Will Groupでは、プラットフォームを展開する際に「人」を第一に考える視点を取っています。リーダーシップがテクノロジーの次の波を乗り越える鍵となるため、このアプローチは極めて重要です。SS&C Blue Prism社の最近のレポートでは、ビジネスリーダーの84%がAI導入による働き方革新の可能性を認識している一方で、75%はその導入が困難であると感じています。私たちは、効率性、拡張性、そして人間的なつながりのバランスを取りながら、常にフィッシングやその他の詐欺的手法で私たちやクライアントを搾取しようとする脅威から必要な保護行う必要があります。
今日のリーダーの戦略に求められるのは、従来のプロセスの先を見据えることです。私たちは、単にプロセスを加速させるだけでなく、テクノロジー導入は従業員に力を与えるとても重要なこととして捉えなければいけません。鍵となるのは、私たちがどのように協業し、革新していくかにおいて自らを差別化するための、適切なバランスを見つけることです。
私の願いは、人々が自分は見てもらえている、支えられている、そして真につながっていると感じられるからこそイノベーションが生まれる、そんなデジタルな職場を私たちが作りあげていくことです。将来最も有望なテクノロジーだと呼べるものは、単なる生産性だけでなく「人の存在感(プレゼンス)」を育むものだと思います。それは、人とビジネスプロセスの間に架け橋をかけ、国境、ブランド、文化を越えた多様なチームが、どこにいても働き、成長し、帰属意識を持てるようにするものです。すべてのリーダーにとって重要な問いは「あなたは自分の組織をどう形成していますか?」です。
執筆者:ロイ・リム

ロイ・リム(Roy Lim)Will Group Asia Pacific、テクノロジー・ネットワーク・セキュリティ担当シニアマネージャー
1991年より30年以上にわたり、情報技術(IT)分野でキャリアを重ねる。ヘルスケア、金融サービス、政府機関、ITアウトソーシング、そして人事・人材ソリューションに至るまで、多様な業界でITサービスマネジメント、プロジェクトリーダーシップ、サイバーセキュリティを専門としてきた。