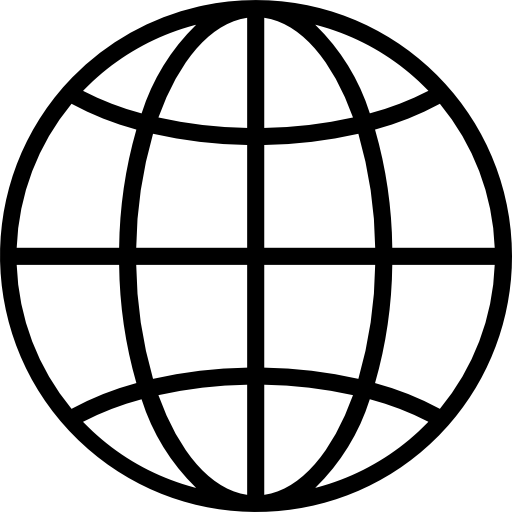インタビュー担当: ローズ タン
被面接者: 芝崎公哉 (GJC 代表)|
G 創刊号では、「文化がもたらす変革」をテーマに、組織文化・社風が企業だけでなくその中にいる個人にどのような影響を与えるかを考えます。今回は、シンガポールの多文化環境で人材紹介会社を築き上げ、10年以上にわたりリーダーシップを実践してきた芝崎公哉氏にお話を伺いました。透明性のあるコミュニケーション、チームワーク、文化理解がGJCの成功にどのように寄与したかを明らかにしていきます。
GJC文化の進化と土台
多様性のあるシンガポールにおいてGJCを十年以上率いてきた中で、市場から求められる企業文化や社風に変化などはありましたか?また、GJCはどのようにしてその変化に対応してきたのでしょうか?
2013年にシンガポールへ来た際、GJCにはすでにチームワークを以て顧客に良いサービスを提供しよう、という強い信念を持っていました。私たちは全ての候補者と対面で面接を行い、紹介先での勤務開始日には紹介先企業に同行するなど、候補者との関係構築に注力していました。
その後、大きな変化として感じたのは、「内向きの文化」から「外向きの文化」への転換です。当初は社内サポートやポジティブな雰囲気作りを目的としたチームワークが中心でした。しかし、それだけでは十分ではないことに気づきました。本当の意味で成功するためには、市場やクライアントの変化するニーズに気づき、行動できることが必要です。
これにより、より専門的で技術的な社内コラボレーションへとシフトしました。
「思いやり」の文化から「思いやりと競争」の文化へ進化したと言えます。この競争は敵対的なものではなく、お互いを高め合いながら価値を提供するものです。
また同時に、透明性も大切です。社内でのミスや間違いについても隠さずに共有し、どうすれば改善ができるか、を全員で考えます。ミスを責めるのではなく、改善策を考える。それぞれのメンバーの建設的な姿勢こそが、弊社の成長の基盤だと考えています。
この「ミスを責めない」という文化はどのように機能しているのでしょうか?ミスをシェアするという社風はどのように成り立っているのですが?
このプロセスには慎重な管理と指導が必要です。まず、報告を受ける側、マネジメントサイドに、起きてしまったことを責めない、という意識を持たせる必要があります。そしてその責任を追及する代わりに、外部への影響を最小限に抑えることに議論をフォーカスさせます。その後、社内で学びのセッションを実施します。このセッションは調査ではなく対話です。参加者全員が客観的であることが重要です。
そこでは、ミスがあったことは認めつつ、それを防ぐためには何ができるかという学びに焦点を当てます。この過程ではミスについて共有し、それぞれが解決策や予防策を考え実行します。このような環境では、人々がミスを認め、それから学ぶ場として機能します。
異なる文化的バックグラウンドを持つ新しい社員に GJCの文化・社風を紹介する際、何か特別な研修を運用していますか?
基本的には大きく変わらないと思います。強いて言うなら、採用プロセスにおいて、当社の文化や業務スタイルについて十分説明します。その上で国籍に関係なく価値観が一致する候補者を選びます。このようにして最初から強いフィット感を確保しています。
国籍による文化的適合性ではなく、組織文化への共感度を見ることが重要です。当社チームは多様なバックグラウンドを持つメンバーがいますが、CORE VALUESへの共通認識があります。この一貫性こそが、新入社員の増える成長期においても変わらない社風を維持するための鍵となっています。
GJC では、離職率が低く、長期的キャリア形成が可能となる理由について教えてください。
人材紹介業界は業界として離職率が高い傾向があります。
しかしGJCでは、自分自身の貢献度を感じる社員ほど長く働いています。これは、候補者・クライアント、そしてチームに対する貢献度です。この目的意識は国籍問わずチーム全体に浸透しています。
結果として、この目的意識が強い帰属意識につながります。当社では部門間で協力し合いながら成長し、一緒に成功や失敗から学ぶ環境・社風があります。技術的スキルだけでなくコミュニケーション能力や共感力などソフトスキルも重視しています。社員には自己成長への責任感と、それを支援するリソースやメンターシップも提供しています。その結果、多くの社員から「入社時よりも能力と自信が向上した」と言われます。それこそ真の定着率の指標だと思います。
人材育成とリーダーシップ論
新しいリーダーとして中間管理職になる社員へどんなアドバイスがありますか?
最も重要なのは「適応型コミュニケーション」です。透明性だけではなく、それぞれの状況や個人に応じてコミュニケーション方法を変えながらGJCのコアバリューを伝えることです。
リーダーシップに正解はありません。新しいマネージャーには、自分らしいスタイルから始めつつ、先輩や上司からのフィードバックや結果によって柔軟に変化することを勧めています。ただし、このトライ&エラーには明確且つ一貫性ある説明が不可欠です。方針などを変更する前にはその理由や期待される成果についてチームへきちんと説明し、メンバーが抱える不安や懸念点について早期段階で意見交換できる場を設けるべきです。
様々な決断を迫られるリーダーは時に孤独を感じます。新たにリーダーとなる社員も例外ではありません。でも、彼らは一人ではありません。
『マネジメントチームへようこそ』といった具合に、他のリーダーたちとの情報交換や相互アドバイスなどができる機会を設けることで、孤独感の解消と、マネジメントの一枚岩、を実現できると考えています。
多くのリーダーは、メンバーから正直なフィードバックを集めるのに苦労しています。心理的安全性を築き、正直なコミュニケーションを促進するために最も効果的な方法は何ですか?社風はどのように関与しているとお考えですか?
本当に正直なフィードバックを得ることは、簡単ではありません。リーダーは、完全にフィルターのかかっていない回答を得ることはほぼ不可能であることを理解しなければなりません。しかし、強い関係性を築くことでそのギャップを埋めることはできます。リモートワークや柔軟な働き方により、さらに難易度が上がっているように感じますが、それでも私たちは「人材ビジネス」に従事しているので、何よりも関係性が重要です。
部下との関係性はすべての基盤になります。
コロナ以降のリモートワークや柔軟な働き方は部下との関係構築を更に難しくしましたが、それでも関係構築は重要です。一緒に昼食やコーヒーを飲む、夕食に行く、その他の非公式な交流を作ることが確かな違いを生みます。リーダーはこれらのコミュニケーションを率先し、チームメンバーに対する配慮や理解を示す必要があります。
会社組織としては、人事チームなどによるフィードバックシステム(投書など)を準備できますが、それが本当に機能するためには、マネージャーとチームの間に強い結びつきと信頼が不可欠です。私がおすすめは「現場に出る」ことです。同じ目線で同じ方向を向いて仕事をすることが、自然なコミュニケーションのきっかけとなり、信頼を生みます。異なる立場から問題に対峙するのではなく、一緒に同じ方向を向いて課題に取り組むことができます。
多文化環境における挑戦と強み
多文化のシンガポールで日系の人材紹介会社を運営することは、課題も多いと思います。文化的な衝突や課題などの例はありますか?
異文化が混在する環境で最も危険なのは「思い込み」です。
私たちは皆、無意識のうちに、自分の文化的背景に基づいた思い込みをします。まず私たちは、自分たちの思い込みが自分特有のものである可能性を認識する必要があります。背景、文化、国籍、さらには性別に関わらず、他者が自分と同じように物事を理解していると思い込んではなりません。シンガポールで10年経った今でも、度々、同じような問題にぶつかることがあります。私は常に自分に言い聞かせます。「思い込むな」と。他者の反応に注意深く目と耳を傾け、疑問がありそうな場合は繰り返し説明し、建設的なコミュニケーションをとることが肝心です。
GJC の多文化的な視点は、結果として強みとなっていますか?
強みだと言えると思います。私たちの多様な国籍、文化、思考は、新しいアイデアやイノベーションをもたらすという強みの一方、メンバー同士の誤解や摩擦といった弱みにもなることがあります。ただし、この強みと弱みの両方の視点を全員が持っておくことで、強みを享受し、弱みをみんなで解決しよう、という動きになります。
ある人がネガティブだと見なす状況でも、別の人は変化や成長の機会と見るかもしれません。この視点の多様性も非常に貴重です。国籍、人種、その他の要因であれ、異なる背景は自然に異なる考え方をもたらし、あらゆる課題や機会の多面的な思考を可能にします。多様な視点は、予期せぬ可能性を解き放つことができるのです。
経営哲学と未来へのメッセージ
「文化がもたらす変革」を探求するにあたり、文化の力に関して、読者に伝えたい最後の考えは何ですか?
私のアドバイスはこれです:自社の文化的な強み、すなわち「カルチュラル・アドバンテージ(Cultural Advantage)社風」を定義し、明確に示し、実践してください。 業界や規模に関わらず、すべての組織には独自の文化的な強み、他社との差別化を図る「秘伝のタレ (Secret Sauce)」のようなものがあります。一般的な限界や業界のステレオタイプに自らを定義づけるのではなく、自社の文化・社風を従業員にとって価値のあるものにしている要素を特定し、それを徹底的に強化・明文化・そして発信してください。
多くの日本企業では、短期的な利益よりも長期的な成長を重視したり、サービスや商品の品質に対するこだわり、継続的改善(改善)など、深く根付いた独自感覚があります。これらは、多様性の求められる現代にこそ、強力な武器となり得ます。価値観や社風を書き出すだけでなく、すべての採用決定、業績評価、クライアントとのやり取りでそれらを体現するべきだと思います。自社の文化的なアドバンテージを非常に明確かつ具体的にすることで、そこに人が共感し、共鳴する。文化的なアドバンテージが、磁石のように仲間を集めてくるのだと思います。
GJC 独自の文化とリーダーシップ・アプローチについて多くを語っていただきました。GJCの文化構築に大きな影響を与えた個人、書籍、または哲学について教えていただけますか?それが、私たちが話してきた課題や機会に特に関連して、あなたのリーダーシップ行動にどのように影響を与えましたか?
パナソニックの創業者である松下 幸之助氏から深い影響を受けました。彼は「失敗したところでやめてしまうから失敗になる。
成功するところまで続ければ、それは成功になる。」と信じていました。彼の小さな一歩への信念は、継続的な改善という日本の考え方から来ています。
私が最も感銘を受けるのは、成功は、困難にぶつかっても、小さな一歩を踏み出し続け、簡単に諦めないことから生まれるという彼の見解です。彼は、「失敗」とは単なる停止点であり、前進し続ければ道は見つかると強調しました。
私たちがシンガポールで初めてチームを拡大したとき、「日本式」の経営スタイルを押し付けようとはしませんでした。私たちは「一歩一歩」のアプローチを取りました。ローカルメンバーに心を開き、様々なコミュニケーション方法を探ってきました。実に多くの間違った選択をし、つまづくこともありました。それでも、前進し続けて来ました。
もう一つの例は、弊社の営業アプローチです。私たちは短期的な成功を求めません。代わりに、お客様との長期的な関係を築きます。お客様の変化するニーズを理解し、一貫して価値を提供する努力をします。そう一歩です。