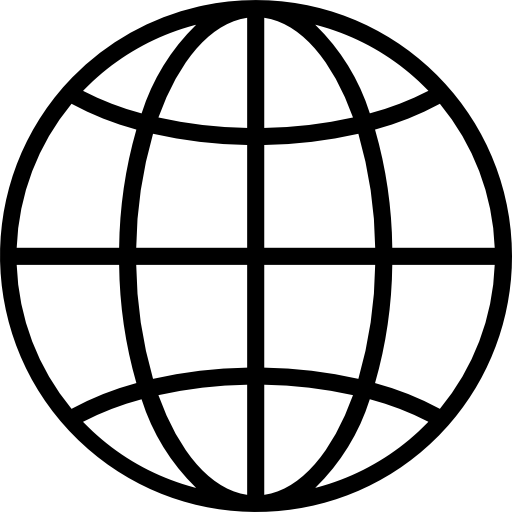ルーティンワークからの解放とモチベーションの創出:AIは「仕事の目的」をいかに再定義するか
Jocelyn
on
August 29, 2025
インタビュー担当:川頭 裕平、ローズ タン
渡邊 仁氏 (Autofusion Pte. Ltd. 代表)|
今回のインタビューでは、AI、ビジネスインテリジェンス、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)等の自動化技術を活用したDX推進を専門とするコンサルタント兼ソリューションアーキテクトの渡邊仁氏にお話を伺い、画期的なテクノロジーがいかに職場を変革するのかを語っていただきます。同氏は革新的なAIエージェントを開発する傍ら、スタートアップ企業で技術顧問としてアドバイザリー業務も手掛け、イノベーションの文化を育む上で、従業員のモチベーションの創出とコミュニケーションが持つ重要性を強調しています。渡邊氏は、人とAI等の自動化技術が調和して共存し、誰もが自身の夢を追い求めることができる未来を描いています。
要点
- AIは従業員の働き方をどう変革するのか? AIは反復的なタスクを自動化し、従業員が付加価値の高い創造的な業務に集中できる環境を提供することで、最終的に仕事への満足度と生産性を向上させます。
- 企業におけるAI導入の最大の障壁は何か? 社内にデータが散在しており、AIが活用できる状態にないこと、及びAI活用に関する長期的なビジョンの欠如が大きな障壁となります。AIの導入に成功するには、長期的なビジョン、データ基盤の整備、そして、視座の面も含む従業員のAIリテラシーの向上が必要です。
- リーダーはどのようにAI導入を促進し、従業員の不安を解消できるのか?「AIをどう活用していくのか」という明確なメッセージと共に、実際に現場で利用するプロトタイプを早期に公開し、従業員を積極的に巻き込んで改善を進めながら、各従業員のAIに対するオーナーシップの感覚を育むことです。
- AIは人間の仕事を奪うのか、従業員はどのように備えるべきか? 将来的にはAIが単純作業は全て担うようになるでしょう。一方で、AI自体にモチベーションはありません。AI時代においては、各個人は”本当にやりたいこと”を追求し、AIはそれを実現するための頼もしい味方として活用できると考えれば、これほどワクワクする時代はないのではないでしょうか。
- テクノロジーを受け入れるためにリーダーが今すぐできることは何か? リーダーはまず自身がAIを積極的に活用する事から始め、AIをどう活用していくのかという明確なビジョンを発信すると共に、AI活用を評価指標などに落とし込むという事も一つの効果的な施策になります。
- 従業員とAIの関係は今後5年間でどのように進化するのか? 人材の観点で言えば、ビジネスパーソンと企業のマッチングにおいて、AIは採用の精度を大きく高めるでしょう。また、ルーティンワークはAIが担うようになるため、単純な”仕事の速さ”自体にあまり価値はなくなり、各個人のモチベーション・創造性が人材にとって不可欠な資質となるでしょう。
ミッションの起源:つまらない仕事をなくす<
渡邊様のミッションとして掲げていらっしゃる「つまらない仕事をなくす」というテーマについて、まずお伺いできればと思います。このミッションを掲げるに至った背景や経緯について、お聞かせいただけますでしょうか。
はい。まず、新卒で入社した大手メーカーでの経験が非常に大きいですね。私はソフトウェア開発部門に配属されたのですが、そこで非常に驚いたことがあります。組織として取り組んでいる内容は非常に先進的なものだったのですが、各従業員のレベルで見ると、多くの方が日々驚くほど単調な作業に追われている光景を目の当たりにしたためです。例えば、会議の調整や経費申請、クライアントの請求書作成、決裁書類の回覧・承認作業などですね。私は大学で物理学を専攻し、大学院でAIの研究をしていた事もあり、「社会人の人達はどのような仕事をしているのだろう」と入社前は期待を大きく膨らませていたのですが、これほどの大企業で多くの人々がいわゆるルーティンワークに日々追われているという事実は、大きな衝撃でした。
もう一つの大きな出来事は、ハードウェアの設計部門にいた同期の話です。新製品の試作品を開発するにあたり、どの部品がいくつ必要になるかを何万行もある巨大なExcelの部品表から算出するという業務があり、そのために彼は毎日夜遅くまで残業をしていたのです。当時、私はExcelマクロが書けたので、お昼休みなどを使ってその業務を自動化するマクロを組んだところ、彼が何時間もかけていた作業が数分程度で終わるようになりました。彼は残業から解放されただけでなく、創出された時間で、本来やりたかった設計業務などのより高度な業務に集中できるようになり、非常に喜んでくれた事を今でも覚えています。この時、自動化によって時間を創出し、誰もが本当にやりたいことに集中できる環境を作る事は、なんて素晴らしいことなんだろうと実感しました。
それが2017年頃で、ちょうどRPA(Robotic Process Automation)が登場し、「働き方改革」が大きな潮流となった時期でした。この頃に、私は本格的に自動化の道を追求したいと決意し、RPA・DX推進の専門部署があったコンサルティングファームに転職しました。まだDXという言葉が新しかった頃でしたが、様々なクライアント企業で、試行錯誤しながら業務の自動化を進めていく中で「あなたのおかげで早く帰れるようになった」といった直接的な感謝の言葉を頂く機会も多く、そのダイレクトなフィードバックが非常に嬉しく、今でも私の原体験として残っています。
リーダーの目線:AI導入時の壁、その乗り越え方
新卒時代を含む業務自動化のご経験が、まさに原体験になっていらっしゃるのですね。テクノロジーの活用によって創出された時間で、早く帰宅して家族や自分の時間を大切にできますし、本当にやりたいことのために時間を使うこともできる。まさしく「時間」が重要なテーマなんですね。
企業やリーダーが懸念するのが、導入に必要な工数やコストの観点だと思います。一方で、導入してみなければ具体的な効果がわからないため、最初の一歩を踏み出すのに大きなハードルを感じられる声をよく聞きます。この最初のハードルを乗り越えるために、渡邊さんはどのようなアドバイスをされますか?
それは、企業のビジョン、特にどれだけ中長期的な視点を持てるかにかかっていると思います。もし現場の短期的な最適化だけを追求するのであれば、新しい自動化ソリューションの導入やAI活用は、それまでの業務フローを抜本的に変える事になるため、初期の導入コストや新しいやり方への順応の観点も含め一定の難しさがあります。多くの人にとって、これまでのやり方を抜本的に変えるのではなく、それまでのやり方を続けるほうが精神的には楽だからです。これはAIに限った話ではなく、どれほど楽になると聞かされていても、スマートフォンを使い始めた頃、最初は誰もが難しいなと感じた事と同じ話かと思います。しかし、今後の労働人口の減少やAIの進化といった長期的な視点で見ると、最初のハードルを越えるその必要性が見えてくるはずです。
AI導入の成果はすぐに出るとは限りません。というのも、データ整備やリテラシーの観点も含め、ほとんどの企業でまだ、AI導入ですぐに効果が出るような土壌が整っていないためです。つまりこれは、短期的にわかりやすい成果を取りにいくような話ではなく、長期的かつ持続的に大きな成果を取りにいくための基盤作り、つまり投資に近い位置付けになります。これは相応の体力、つまりリソースがある企業でなければ難しいという側面は当然ありますが、半年~1年程度では大きな差が出ない場合も、3年、5年と経った時に指数関数的に大きな差が開いている可能性があります。今後更にAIの進化は加速していく事が予想されるため、今からアクセルを踏んでおかなければ、気づいた時には事業自体が破綻しているという事にもなりかねません。これは一過性の効率化対応ではなく、本格的なAI時代の到来に向けた基盤作りとして議論する必要があります。
そして、その基盤ができていれば、今後の更なるAIの進化を含む新しいテクノロジーが登場した際のキャッチアップ、及び、効果の刈取りが非常に速くなります。つまり、AI時代においては、段階的にAI-Readyな企業へ変革していく必要があるという事です。
現時点においては、AI導入で最も大きな問題となるのが、社内データが散在していたり、アナログな紙媒体中心で整備されていないケースです。どれだけ今後AI自体の性能が上がったとしても、必要なデータが整備されていなければAIの本当の価値を引き出す事はできません。実際のところ、これまでデジタル化やDXを怠ってきた企業がいきなりAIソリューションを導入したり、優秀なAIエンジニアだけを採用しても、必要となるデータにアクセスできず、プロジェクトが上手く進まないという結果になってしまうでしょう。現在AI活用の恩恵を最も受けられているのは、これまでデジタル化を含むDXに泥臭く、試行錯誤を重ねて取り組んできた企業になります。
AI導入でわかりやすい効果がすぐに出るとは限りませんが、中長期的な視点でAIの活用戦略をどう位置付けていくかという事が、どの組織にとっても今後重要なテーマになるのではないでしょうか。一定のコストと変革が求められる以上、AI活用に取り組む事も当然、一定のリスクははらみますが、一方で、AI活用に今アクセルを踏まないという意思決定にも、今後のAI時代においては、それ相応のリスクをはらむ事になると思います。誰も正解を持っていない問いであるだけに、ここはまさにリーダー達のテクノロジーに対するビジョンが問われているのではないでしょうか。
AI導入の成果はすぐに出るとは限りません。むしろ企業の中長期的な成長に向けた投資に近い位置付けになります。真の自動化を実現するには、AIが活用できるデータが整備されている必要があり、加えて、従業員の間にAIリテラシーを醸成していくことも重要です。まさに今、リーダー達のテクノロジーに対するビジョンが問われています。
AI導入と適応:従業員を不安から安心に
その長期的なビジョンを、短期的な成果を重視しなければならない企業が理解と実行をするのは難しさがありそうですね。「目の前に分かりやすい成果があるじゃないか」という現場目線とのギャップがどうしても生じるので。AIを導入する際、現場が感じるストレスは確かにあります。また、先ほどおっしゃられたように、従業員のITリテラシーを育んでいく必要もあります。これまでのご経験の中で、従業員のITリテラシー向上という課題に、どのように取り組んでこられましたか?
従業員の視点ではやはり、「これで自分の仕事が本当に楽になるのか?」という事が最も大きいかと思います。よくある間違いは「データが重要なので、システムの入力をちゃんとしてくれればAIが使えます」といった指示を最初から一方的な形で押し付けることです。現場としては、これまでのやり方を変える以上、その手間に見合うリターンがなければ、当然これまでの業務を変えるモチベーションが湧きません。ですから、AIの導入に関わらず、新しいソリューションの導入で私が最も重視しているのは、初期段階でプロトタイプやデモを作成し、まず業務ユーザーに触ってみてもらい、体験してもらうことです。「これなら使いたい」と実体験としての肌感をまず持ってもらい、現場目線でのフィードバックを受けながら、関係者間で最終的なゴールが見える状態を協力して作っていきます。
私が最も重視しているのは、初期段階でプロトタイプやデモを作成し、まずユーザーに試してもらうことです。「これなら使いたい」と感じてもらうことで、最終的なゴールが見える状態を作ります。
生産性を高め、無駄な業務を削減し、より価値の高い仕事に集中できる環境を作りたいと考えている中で、このアプローチができるかどうかが非常に大きな差に繋がりそうですね。
少し話は変わりますが、現場の観点だけではなく、マネジメント層の観点からも今最も重要だと考えているのが、適切な情報の「可視化」です。多くの企業で今も蔓延しているのが、報告のためだけの資料を作成する文化です。様々なシステムからデータを抽出してまとめ、資料を作成して管理職に報告資料として提出する。この作業は、作成する側はもちろん、資料作成を依頼する管理職側にとっても、依頼した資料が期限までになかなか上がってこなかったり、やり直しが発生したりと、大きなストレスとなります。
そこで私が自動化推進プロジェクトにおいてクライアントと実践したのが、プロジェクト全体の進捗状況とROIを可視化するダッシュボードの構築でした。これまでは四半期毎の報告の集計が非常に煩雑かつ、マネジメント層としても現場の実態がタイムリーに見えないという悩みがありましたが、このダッシュボードの構築により、現場の作業時間の削減と共に、マネジメント層が随時状況を確認できるという状態を構築する事ができました。この結果、定期的な進捗報告の会議を廃止し、問題が発生した時だけアドホックに集まり、関係者で集中して議論するというやり方に変える事になり、プロジェクト全体の改善のスピードと品質の向上に寄与しました。
このように必要な情報を随時可視化し、透明性を高めておく事で、マネジメント層も「今、状況はどうなっているのか」と気を揉んだり、報告資料の作成を依頼するストレスから解放されるようになります。私も若手の頃は、報告のためだけの資料作成にかなり時間を費やした経験がありますが、いわゆる報告に関する作業が減り、ディスカッションや次のアクション検討がタイムリーに行えるようになる事は、現場視点でもマネジメント層の視点からも重要だと思います。
まず、必要なデータを可視化することで「報告のためだけの会議」をなくす。そして、そのデータを見て「次に我々は何をすべきか」というアクションの議論に集中する。さらに一歩進めて、データの可視化に留まらず、AIを活用してインサイトを導き出すことも可能です。「現状はこの通りです。そして、AIの分析による提案はこちらです」といった形で、これまでコンサルティングファームに依頼していたような分析を、徐々に内製化し、かつ、タイムリーに実施できるようになります。
つまり、現状が常に可視化されている上に、AIの改善提案も参考にして、関係者間でディスカッションが始められるため、より質の高い議論に時間が使えるようになります。このようにして、かつて単純な作業に費やしていた時間を、より付加価値の高い仕事へ充てられるようになると思っています。
データを可視化することで、「報告のためだけの会議」をなくす。そして、そのデータとAIのインサイトをベースとして「次に我々は何をすべきか」というアクションの議論に集中する。
AIやテクノロジーが当たり前となっていくこの時代において、従業員はどのようなスキルセットやマインドセットを持っているべきでしょうか?また同時に、リーダーはどのようなアプローチでそれを育んでいけるのでしょうか?
AI時代においてはまず、リーダーからのメッセージとして「これまで優秀とされてきた人材の定義が変わった」と明確に打ち出すべきだと考えています。これまで優秀とされてきた、ロジカルシンキングが得意、指示されたタスクを高速に処理できるというところは、ある種AIの最も得意とする領域なので、相対的に付加価値が小さくなっていきます。一方で、多少粗削りでも良いので、ゼロイチの提案ができる人、少し変わった斬新な切り口で物事を考えられる人の価値が高まってきています。つまり、決まった正解を出す事よりも新たな問いを立てられる力の方が重要なので、むしろこれまでは推奨されなかったような、あるいは私が新卒の頃などには怒られていたような行動こそが評価される時代に突入しています。一方で、リーダーからの明確なメッセージがなければ、従業員は「今何が期待されているのだろうか。私達はこのままで良いのだろうか」と不安を抱え、積極的な行動が取れなくなります。AIなどのテクノロジー活用に関しても、組織として何が求められているのかという事を明確にメッセージすることで、従業員のエンゲージメントを高め、安心して業務を行う環境を作る事ができます。
2つ目は、組織のピラミッド構造についてです。私は大手のクライアントと仕事をする機会も多いのですが、大きな組織の中では、いかにして従業員の当事者意識を維持できるかという事が常に課題となります。どれだけ組織のピラミッドをフラットにしようとしても、事業を運営するためにはチームが必要であり、大企業の性質上、組織構造は自然と大きくなる傾向にあるためです。
しかし、AI時代になるとこの構造が大きく変わってきます。AIが労働力の主役となっていく時代においては、従来のような、人中心で構成されるピラミッド構造ではなく、人間が担うべき領域が企画・マネジメントのような上層に移行し、実行領域である下層はAIが担う形になります。
これはAIに置き換えられて人が減るという事ではなく、同じ人員数で、ピラミッドのサイズは維持したまま、ピラミッドの数自体を増やせるという事です。今後はむしろ、数人程度の人員で構成され、多数の強力なAIを労働力として持つ、少数精鋭での高付加価値なチームを作る事が一つの目標になってくるでしょう。こうなると、ある意味では全員がリーダーであるとも言えます。
なるほど。「うちの会社で本当にそれをやっても良いのか?上手くいくのか?」という疑問が湧く瞬間もあると思います。全社的に一斉に方針を宣言することに難しさがある場合は、特定のチームや部門に絞って試験的に試行していくのが一般的なのではないでしょうか。
はい、まずは少人数のチームで試行してみる。そして、そこで成功したモデルを段階的に展開していくというアプローチもありだと思います。新しい働き方を試行しつつ、これまでの人ベースのピラミッドから、AI時代のピラミッド構造へと移行していく事できれば、従業員が大きな当事者意識を持てるようになると思います。いわゆるトップダウン的な指示に元でのやらされ仕事ではなく、AIという強力な味方をつけ、各人が主体的に方針を立て、物事を進められるようになれば、仕事はどんどん楽しくなっていくのではないでしょうか。
AIと仕事の未来:”人”中心の視点
AIの進化は止まりませんね。同時に、以前からよく議論されている懸念があります。AIの台頭によってこれまで人が担ってきた仕事や職場における自分の「居場所」が失われるのではないか、という不安です。この点についてはどのようにお考えでしょうか。
DXの推進:東南アジアにおけるAIの今後の展望
ここからは、目線を我々がビジネスを展開している東南アジアやシンガポールに移したいと思います。渡邊さんは2024年にシンガポールに移られたとのことですので、ちょうど1年ほどになるかと思います。この地域における日本企業のDXの課題、そして今後の展望や期待について、どのようにお考えでしょうか。
そうですね。国を超えた話という意味では、AIはいわば「潤滑剤」のような役割を果たしてくれると思います。言語の翻訳はもちろん、それぞれの文化や歴史、価値観の相互理解の側面も含め、異なる国同士の間に立ち、相互の協力を促してくれる存在として活用できるため、この分野の進展は間違いなく加速していくでしょう。これは海外から日本に来る方々にとっても同様です。これまでは言語や文化の壁が非常に大きな障壁として存在していましたが、AIがそれらを取り払ってくれるようになります。例えば、製造業などでよくある話で、現地で工場を立ち上げ、現地スタッフを雇用したものの従業員がなかなか定着しないといった問題がありますが、これは事業計画の段階では日本からだと見えにくいものです。
しかし、今はAIが使えるので、「特定の地域で事業を行う上での留意点」を商習慣や文化、歴史や人々の価値観の側面も踏まえて非常に詳細な粒度でわかりやすく教えてくれます。もちろんこれだけでは十分ではないですが、これまでであれば収集するのに多大なコストがかかっていたような、非常に価値のある1次情報を瞬時に提供してくれるでしょう。逆に、東南アジアの起業家が日本市場への進出を検討する場合も、事前調査や現地とのコミュニケーションを強力にサポートしてくれるようになるため、これまでかかっていた大きな労力を削減し、より本質的な取り組みに集中できるようになるでしょう。このように、AIが国家間の良い潤滑剤として機能し、国を超えたプロジェクトや協力関係が大きく進んでいくのではないかと、非常にワクワクしています。
今のようなAIがまだなかった頃、オフショア開発として、インドのエンジニア達と仕事をした経験がありますが、まさにその時に課題を感じました。レスポンスの速さや会議調整などの時間に関する面もそうですが、軽微な意思疎通における認識齟齬が頻繁に発生し、コミュニケーションの難しさがあったのです。それに加えて、現地では転職を繰り返しながら給与を上げていくのが当たり前という文化があり、現在の業務に就きながらも、常に次のキャリアを考えている、といった働き方に対する価値観の違いもありました。日本の当たり前は海外の非常識を言われているように、そういった文化や価値観のギャップを、AIがうまく補ってくれるのではないかと考えています。AIはどちらの立場にも立って考える事ができるという所が、コミュニケーションを促進していく上で大きな強みだと思っています。
リーダーのための指南書:AIが育むエンパワーメント
今回のお話を通して、テクノロジーやDXがもたらす好影響について大変よく理解できました。リーダーがテクノロジーを導入し、より付加価値の高い仕事を生み出していくために、極端な話ですが明日からでも起こせるような最初の一歩があるとすれば、何から始めるのが良いでしょうか。
まず確実に必要なのは、リーダー自身が実際にAIに触れてみることです。ChatGPT, Claude, Geminiを始め様々なツールが登場していますが、これらを自ら試すことが必須だと思います。ただ、その上で非常に重要なのは、AIに対する「自分なりの哲学」を磨いていくことです。というのも、AIの使い方に唯一の正解は存在しないからです。そのため「自社ではどのようにAIを活用していくのか」という事を社内で徹底的に議論する必要があります。そうした議論や方針がないまま、ただChatGPTのようなツールを導入しただけでは、従業員はどの程度AIを使えば良いのか、またどのような方向性で使っていけばよいのかが分かりません。
海外のある有名企業で、従業員の評価項目に「AIをどれだけ活用したか」という指標を導入したという話は非常に面白いと感じました。
もちろん業種にはよりますが、特にホワイトカラーの場合、個人の生産性や仕事ぶりを測る上で「AIをあまり使っていません」という従業員は、AI時代においては率直に言ってしまえばローパフォーマー、つまり生産性が低いと見なされる可能性があります。そのため、AIの活用度合いを評価指標に加えることで「AI活用が会社の方針として求められている」という明確なメッセージになります。これは社員がAIを活用する明確なモチベーションになる上に、AIにもともと関心が強かった人達も、安心してAI活用に取り組めるようになるでしょう。さらに、評価面談などで、リーダーが現場から「このようなAIの使い方が効果的でした」といったフィードバックを受け、その学びを組織全体に展開していくというような好循環も期待できます。会社員として勤務している友人達と話していても「うちの会社ではAIをどこまで使っていいのか、AI活用が推奨されているのかどうかがよくわからない」という声をよく聞くので、単純な呼びかけではなく、AIの活用を評価指標に組み込むという事は明確なメッセージとして機能するのではないでしょうか。
また別の例として、新規事業の提案時には、「その業務はAIでは実行できないか、十分に検討したか」を問う仕組みを導入している会社もあります。新規事業を提案する際は、通常「この事業を開始する際にどれだけの人的リソースが必要か」といった計画を立てると思います、そのプロセスにおいて、「なぜその業務をAIではなく人間が担当する必要があるのか」を明確に説明することが求められます。これにより、提案者はまず「これはAIでできないか」と自問自答するようになります。その上で、人間でなければ難しいと判断した場合にのみ、人的リソースを要求するという流れになります。この「AIでできないだろうか」と常に考える仕組みは、AI時代において、各従業員達がAIへの洞察を深め、リテラシーを高めていく上で良いトレーニングになるのではないだろうかと感じました。このように、組織や社員にAIの活用を促す「仕組み」をどう構築していけるかが非常に重要なポイントになると思います。
なるほど、確かにそうですね。リーダーが自分で試したり、単に「AIを使っていきましょう」と発信するだけでなくそれを仕組みとして組織にしっかりと落とし込んでいくことは非常に重要ですね。
リーダー層がよくあるメッセージや動画等で呼びかけるだけでは不十分で、「評価制度に組み込みます」といったように会社として具体的な仕組みまで作っているとなると、従業員にその本気度が伝わるのではないでしょうか。
例えばワーキンググループのようなものを立ち上げ、AI活用について継続的に組織で検討していくのも一つですし、評価制度に関しても、自身の利用状況だけでなく、「自身の新たな学びや知見をチームにも共有しましたか?」といった項目を加えても良いと思います。AIの進化はあまりにも速く、私自身すべてをキャッチアップする事は既に不可能になってきています。つまりこれは、組織的な取り組みであり、自身の活用実績だけでなく「知識を共有してチーム全体の生産性向上に貢献したか」という点も評価することで、良い機運が生まれ、学びの相乗効果も期待できます。
新しい物事に取り組む姿勢には、様々な要素が含まれていると思いますが、スキルの巧拙に関わらず、そうしたモチベーションや意識を醸成していくことこそ、リーダーの役割だと思います。
人と自動化が生み出す効果:採用と人材における今後5年間の展望
最後に、私たち「働く人」と「オートメーション」の関係性についてお伺いします。この関係はもちろん今後も続いていくと思いますが、5年後という比較的近い将来においてその関わり方はどのように変化していくとお考えでしょうか。
まず採用や求人の領域で言いますと、AIによってマッチングの精度が劇的に向上するでしょう。これは仕事を探す個人にとっても、人材を募集する企業にとっても同様です。マッチングの精度が大きく高まるので、私たち個人がすべきことは、本当にやりたいことをある種「わがまま」なくらい明確に示していくことです。そこで忖度をして、いわば万人受けするような個性のない表現にしてしまうと、AI側も本人の意図を明確に読み取れなくなります。逆に「これがやりたい」と明確に意思表示をすれば、これまで選択肢が非常に少なかったような場合でも、AIによってマッチング対象の母数もマッチングの精度も飛躍的に向上するため、AIが最適な候補を見つけてきてくれるようになります。
逆に企業側としても曖昧な求人票や業務内容を提示するとAIには真意が理解しにくいでしょう。双方ともが明確な意思表示をすることが重要です。選択肢は増えるのですから、それぞれが忖度する事なく自分達の目指す目的にこだわった上で、AIにマッチングを任せるべきです。
先ほど述べたように、AIによっていわゆる生産性は今後飛躍的に上がっていくと思いますが、モチベーションに関しては別問題で、AIに内発的なモチベーションはありません。私が目指すオートメーションの理想の姿は、強いモチベーションはあるもののリソースが不足している人々を支援することです。例えばこれまでであれば、意欲はあるが、資金がないのでなかなか新しい取り組みを始められなかった、といった人達に、オートメーションやAIといったテクノロジーを提供し、個人や組織の能力を拡張していく。そして、誰もが本当にやりたかったことに挑戦してワクワクできる、そんな時代にしていきたいですね。
逆に、どれだけタスク処理が速く、いわゆる地頭が良くても、「これがやりたい」という強いモチベーションがない人の価値は、相対的に下がっていくでしょう。そして、私自身はそれ自体は非常に良い事だと思っています。今後のAI時代に真に問われるのは、私たちが「タスクをいかに正確に速くこなすか」というこれまでの価値観から脱却し、ある種、子どものように「わがまま」になれるかどうかです。何かをやりたいという強いモチベーションがあり、その意思を示せばAIが助けてくれます。
元々オートメーションの道を志した理由もここにありますが、私のミッションは、個人や組織の能力を拡張し、全員が本当にやりたいことをやっているという状態を実現することです。つまらないけれど必要な仕事に関してはAIに任せてしまえばよく、本当にやりたい事を追求して良い、むしろ、それにしか価値がない時代が近づいてきていると思います。
「仕事が速い人/遅い人」という概念そのものがなくなるのではないかと感じました。誰もがAIを使うことで一定のスピードを担保できるようになるため、「仕事の速さ」によって生じていた優劣がなくなりその点での差別化は失われていくんでしょうね。
ええ、その概念はなくなっていくと思います。問われるのは、意欲があるかどうか、面白いか、クリエイティブか、といった人間的な魅力の点になるでしょう。これまでの「優秀な人」の定義が、大きく変わる時代に突入しているということです。
私自身、エンジニアとしてこれまでは、プログラミング的なスキルが非常に重視されていましたが、今ではプログラミングやテストといった工程の多くをAIに任せるようになっています。そのおかげで、作りたいものをどんどん形にする事ができる上に、事業ドメインや企画領域の検討にも踏み込みながら、常時5つ以上のプロジェクトを並行して進められています。私個人としては、10年前や5年前では夢だったような事が実現できているので、今は楽しくて仕方がないですね。まさに「わがまま」が許される時代、やりたいことを実現できる時代になったのだと思います。これまでつまらないと感じる仕事に従事していた人達や、まだ若い世代の人達も含め、皆が本当にやりたい事を全力で楽しんでいる。そんな未来が実現できたら、本当に幸せだと思いますね。私も今後更に、AIというテクノロジーを全力で使い倒して、自分と周りの人達の夢を叶える活動に邁進していきたいと思います。
まさに「わがまま」が許される時代、やりたいことを実現できる時代になったのだと思います。AIによって、つまらないと感じる仕事に従事していた人達や、これからの若い世代の人達も含め、皆が本当にやりたかった事を全力で楽しんでいる時代の実現を目指す。

渡邊 仁 氏
AI・BI・RPA等の自動化ソリューションを活用した業務自動化のコンサルタント兼ソリューションアーキテクト。株式会社デンソーでソフトウェアエンジニアを経験後、KPMGコンサルティング, IBM等で多数のクライアントの自動化CoEの立ち上げ・リードを実施。大阪大学物理学科卒、奈良先端大情報科学修士。日本にて独立後、現在はシンガポールの Autofusion Pte. Ltd. 代表として、AI ベンチャーの技術顧問も務めながらAIエージェントの開発・推進支援を手がける。
渡邊 仁氏の洞察に満ちた視点は、AIと共に育まれていく仕事の未来について説得力のあるビジョンを示しています。貴社がAI導入の変革を求めソリューション提案に興味がございましたら、jin.watanabe@autofusion-sg.com までお気軽にご相談ください。
AI導入とDXの複雑さを乗り越えるには、戦略的なパートナーシップが必要です。Good Job Creationsは、この道のりにおいて貴社をサポートし、適切な人材とソリューションを結びつけていくよう努めています。
ご質問ご相談はenquiry@goodjobcreations.com.sgまでお問い合わせください。