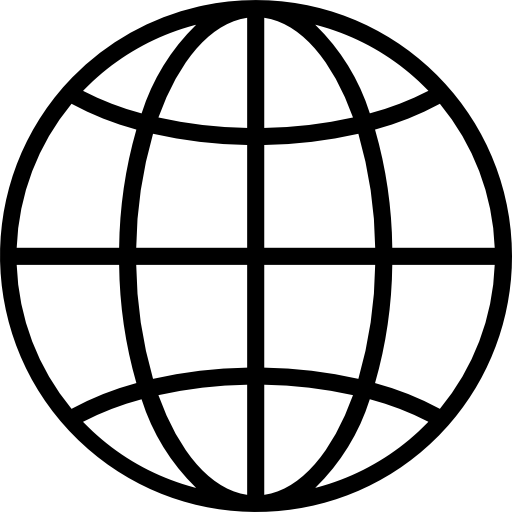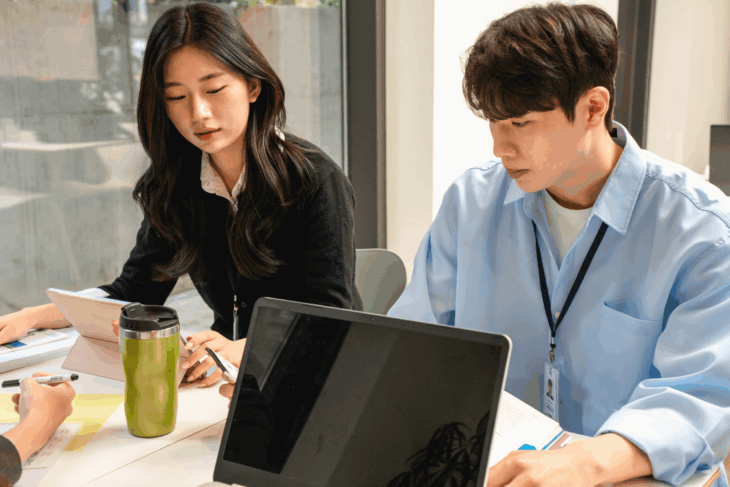マレーシア採用の課題を解決|日系企業向け「人材定着」の新戦略
Jocelyn
on
July 29, 2025
【この記事の要点】マレーシア採用の3つの課題
- 加速する人材獲得競争:外資系・ローカル大手企業が提示する魅力的な条件により、候補者優位の市場が形成されている。
- 価値観のミスマッチ:日本的な雇用慣行(年功序列など)と、現地の若手が求める成果主義・キャリア成長の間にズレが生じている。
- 採用チャネルの限界:従来の人材紹介や求人サイトだけでは、優秀な若手・専門人材へのリーチが困難になっている。
〜人材確保の新たな視点と、企業成長を支える採用戦略〜
2024年、日本とマレーシアは外交関係樹立67周年という節目を迎えました。マハティール元首相が提唱した「ルック・イースト政策」以降、日本とマレーシアの経済関係はより深く、実りあるものになっています。
現在、マレーシアでは1,600社以上の日本企業が活動し、製造業だけで34万人以上の雇用を創出。さらに24,545人の日本人がマレーシアに在住(2022年12月時点/外務省データ)しており、日本企業にとって、マレーシアはまさに“ビジネスと生活の拠点”となっています。
成長市場マレーシアで日系企業が直面する「人材が採れない、定着しない」という課題
2023年のJETROによる『アジア・オセアニア日系企業実態調査』によると、マレーシアは引き続き日本企業にとって魅力的な投資先とされています。一方で、「熟練した有能な人材確保と定着の難しさ」が難しくなっているという声も増えています。
マレーシアの労働需要はQ1 2025時点で1.4%増加(HR Asia調べ)。市場は“候補者優位”となり、スキルのある人材の確保が年々難しくなっています。
さらに、『PWCマレーシアCEOサーベイ2024』では、マレーシア企業の経営層の多くが「スキル人材の不足」を極めて深刻なリスクと捉えていることが明らかにされています。
競争激化の具体例:ローカル大手・グローバル多国籍企業が提示する魅力
- 柔軟な働き方(リモートワークやハイブリッド勤務、フレックスタイム制度など)
- 充実したキャリア開発プログラム(研修、メンター制度、グローバルローテーションの機会)
- 明確でグローバルなキャリアパスと海外勤務のチャンス
日本企業が見落としがちな、現地トップ人材との3つの文化的ギャップ
1. 日本の価値観と現地人材のギャップ
日本企業が重視する価値観と、マレーシアの若手人材が求めるものには、主に以下の点で大きなズレが見られます。
- キャリア成長のスピード感: 日本の「年功序列」に対し、現地人材は「成果主義での早期キャリアアップ」を期待します。
- 「安定」の定義: 日本の「終身雇用的な安定」とは異なり、現地プロフェッショナルは「自身の市場価値を高められる成長機会」こそが安定だと考えます。成長が停滞すれば、転職も厭いません。
- ワークライフバランスの重視: Hiredly社の2025年レポートによれば、69%がキャリアアップを望む一方、長時間労働を望むのはわずか15%です。成長と私生活の両立が必須条件となっています。
総じて、彼らが強く求めているのは「早期のキャリア成長」「ワークライフバランス」「裁量と自由」の3点です。
2. ローカル企業・MNCとの競争
マレーシアのローカル大手企業やグローバル企業は、給与だけでなく、柔軟な働き方や充実した福利厚生で若手人材にアピールしています。これに対し、日本企業の「日本ブランド」は現地人材にとって以下のような魅力と課題が共存しています。
- 日本ブランドの強み:高品質・高水準の製品・サービス、技術力の高さ、そして日本での研修や教育機会などが評価されています。
- 一方での課題としては:厳格なヒエラルキー構造、意思決定の遅さ、そして欧米系多国籍企業と比べて過剰な残業が多いという印象が挙げられます。
こうした現地の認識を理解し、受け入れつつ、柔軟な働き方の導入や明確で魅力的なキャリアパスの提示など、競争力のある雇用価値提案を行うことが信頼獲得と採用成功の鍵となります。
3. 採用チャネルの限界
従来の人材紹介や求人サイトだけでは、特に若手の優秀層や専門スキルを持つ人材にリーチすることが難しくなっています。マレーシアではLinkedInがビジネスパーソンに広く利用されているほか、JobStreetなどのローカル求人ポータルも依然として強力な採用チャネルです。
これらのプラットフォームを活用しつつ、SNSや業界ネットワークを通じて候補者一人ひとりにパーソナルに働きかける「個別アプローチ」がますます重要になっています。例えば、LinkedInでのダイレクトメッセージや、業界コミュニティでのネットワーキングを通じて、候補者の関心やニーズに寄り添ったコミュニケーションを行うことが求められています。
失敗しがちな伝統的戦略:「柔軟な働き方」の本質とは
マレーシアのプロフェッショナル層は、リモートワークやハイブリッド勤務、圧縮労働週、柔軟な勤務時間など「実質的なワークライフインテグレーション」を期待しています。これらはもはや特典ではなく、特に高度なスキルを持つ人材にとっては最低限の条件となっているのです。
CXC Globalの「Future of Work」報告でも、アジア市場における柔軟な働き方の重要性が繰り返し強調されています。
人材戦争を制するための4つの戦略
ここでは、マレーシア在住の日系企業や、日本語を話す現地人材を採用したい企業様に向けて、実践的な採用戦略をご紹介します。
1. 雇用主としての魅力を再定義する
単なる給与条件の提示ではなく、「自社ならではの経験や成長機会」を明確に伝えることが重要です。
例として、
- 世界的に評価される日本のモノづくり理念や、綿密なプロセス管理のトレーニングを受けられる育成制度
- 日本本社との直接連携機会があり、グローバルなキャリア視点を持てる環境
- 安定性とチャレンジ精神が共存する職場文化
を具体的に言語化し、GJCはクライアントの「日本ブランド」を現地市場に刺さる形で再構築・発信するサポートを提供しています。
2. 採用プロセスのローカライズと文化的感度の向上
例えば:
- ジョブディスクリプションには、業務内容だけでなく「事業へのインパクト」「スキル習得機会」を盛り込みましょう。
- 面接では多様な面接官を配置し、双方向の対話を重視。若手マレーシア人材は質問や企業文化の確認を期待しており、一方的な面接は敬遠されます。
- さらに、面接官にはクロスカルチュラルコミュニケーション研修を行い、直接的かつ明確なフィードバックを心掛けることが効果的です。
3. 多層的な採用チャネルを駆使する
SNS広告、リファラルプログラム、そして専門性の高いリクルーター活用を組み合わせましょう。
特に日本語能力や日本企業文化への理解が必要な人材については、GJCのような日本企業向けに特化した専門リクルーターが重要です。豊富なネットワークと業界知識により、アクティブに転職活動をしていない候補者にもアプローチ可能です。
4. 入社後のフォローアップを最重視
採用したその日から「定着支援」が始まります。入社初日から「育成・評価・キャリアパス」が見える構造を用意し、信頼関係を築くことで離職を防ぎます。
- 勤続年数だけに頼らず、透明性のあるキャリアパス設計を行う
- 年1回の評価だけでなく、定期的なフィードバックセッションを設ける
- ローカルマネージャーと日本人駐在員が連携したメンタープログラムを運用し、異文化理解を深める
GJCが提供する、マレーシア採用の「確かな選択肢」
- 業界特化の専門性:日本企業文化と現地ニーズを深く理解
- 多言語対応のコンサルタント:日本語・英語・中国語を自在に操り、本社と現地のコミュニケーションギャップを解消、採用スピード向上と文化的整合性を確保
- 人材不足やスキルミスマッチに強いソリューション提供
- トータルサポート:
- 正社員紹介
- 契約社員/人材派遣
- ビザサポート
- 採用プロセスアウトソーシング(RPO)
- 現地市場動向を踏まえた採用コンサルティングと情報提供
人材課題を、企業の持続的な成長チャンスへ
マレーシアは依然として日本企業にとって大きな可能性を秘めた市場です。
今こそ、「採用=単なる埋め合わせ」から「採用=惹きつけ、育て、残す」へと戦略を転換しませんか?
人材戦略の最適化が貴社の持続的成長を加速します。
マレーシア・シンガポールでの日本人材採用や日本語話者の現地優秀人材確保をご検討の際は、ぜひGJCへご相談ください。