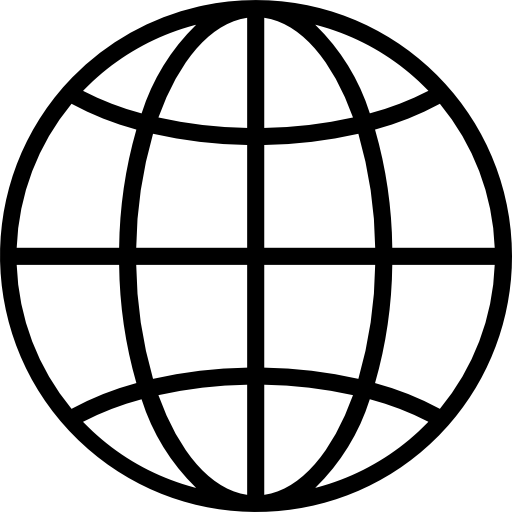-
- 2026年の平均昇給率は? 2026年のシンガポール労働市場では、平均4%の昇給が見込まれています。
-
- 人材を定着させるための最良の方法とは? 競争力のある給与は重要ですが、真の通貨は「信頼」です。透明性の欠如が離職の要因となっています。
-
- どの業界がFWAを導入しているのか? シンガポールでは電子工学、金融、情報通信、運輸、小売業などを含む91%の業界が、何らかのFWA(フレキシブル・ワーク・アレンジメント)を導入しています。
80%の企業が、給与や福利厚生の競争力不足により候補者を失っている現状の中で、各社は報酬戦略の見直しと強化を迫られています。大企業は給与ベンチマーキングなどの施策を進めていますが、この数字は依然として大きなギャップを示しています。
その結果、56%以上の雇用主が「採用難職種」に対して給与オファーを引き上げる意向を示しており、報酬戦略を柔軟に再設計する動きが加速しています。従業員満足度や福利厚生のベンチマーキングは、従業員ニーズとの整合を図り、競争力のある職場環境を構築するための重要な鍵となります。
2026年のシンガポールでは、平均昇給率は約4%と予測されていますが、議論の焦点は単なる昇給幅を超えています。現代の労働者は、より大きな「信頼」「柔軟性」「ウェルビーイング(Well-being)」を求めています。リーダーはこの変化を活かし、自社ブランドを差別化し、持続可能な企業文化を育むべきです。
メンタル・ウェルビーイングはシンガポールのGDPと人材定着にどのような影響を与えるのか
メンタルヘルスや燃え尽き症候群(バーンアウト)は、単なる人事課題ではなく、経済的リスク要因でもあります。
デューク-NUS医科大学とIMH(Institute of Mental Health)の共同研究によると、シンガポールにおける不安症やうつ病による生産性損失は、約1,600億シンガポールドル(S$16 billion)にのぼると推計されています。影響を受けた従業員は年間で平均17.7日多く欠勤し、勤務中の生産性も40%低下していることが明らかになりました。
さらに、61%の従業員がバーンアウトを経験しているというデータもあります。シンガポール企業の62%が予算上の制約により福利厚生設計に課題を感じているとされますが、離職や生産性低下によるコストは、予防的なウェルビーイング施策への投資をはるかに上回ります。
企業は「休暇」を単なる受動的な制度としてではなく、「エンゲージメント」「ロイヤルティ」「生産性」を高めるための積極的なマネジメントツールとして再設計すべきです。
また、柔軟な福利厚生やメンタルヘルス補償は未だ普及途上にありますが、58%の企業がメンタルウェルビーイングに注力しており、従業員の個別ニーズに応じた制度設計が進んでいます。
従来の医療保険や歯科治療、健康診断といった福利厚生に加え、次世代の従業員は「よりパーソナライズされた包括的なケア」を求めています。リーダーはその根本原因に取り組む文化変革を主導しなければなりません。
実践的なステップとして以下の3点が挙げられます:
なぜ「信頼」「柔軟性」「ウェルビーイング」が人材定着を左右するのか
62%の企業が、福利厚生設計の難しさを「予算制約」に起因すると回答し、39%が「従業員ニーズの変化への対応」に苦慮しています。
特に若手世代(ミレニアル世代やZ世代)は、「給与の透明性」を特別な制度ではなく当然の基準と考えています。2024年の調査では、シンガポールの従業員の71%が給与開示に賛成し、72%が採用時の給与交渉にストレスを感じていることがわかりました。
報酬の競争力も重要ですが、人材をつなぎ止める真の通貨は「信頼」です。給与体系の不透明さがこの信頼を損ない、最終的に従業員1人の離職が給与の50〜200%のコストを生む可能性があります。
リーダーは、報酬決定の根拠(成果、相場、社内公平性)を明確に伝える文化をつくることが重要です。これにより、従業員の納得感と尊重意識が高まり、組織リスクやレピュテーション低下を防ぐことができます。
一方で、給与格差の可視化により一時的な反発が起こる可能性もありますが、それは持続的成長と信頼構築のための投資と捉えるべきです。
なぜ「柔軟性」と「雇用の安定性」がシンガポールの人材戦略において重要なのか
2024年に導入されたMOM(人材省)のFWA(柔軟な働き方)ガイドラインは、いまや人事制度設計の基盤となっています。きちんと運用するには、単に柔軟な働き方を提供することにとどまらず、成果ベースの評価ができるようにマネージャーを育成することです。GJCでは、FWAテンプレートおよびリソースキットを通じて、これらのガイドラインを実践的に導入するための支援を行っています。
調査によると、95%の従業員が「給与よりもワークライフバランス」を重視 していますり、特にZ世代の88%がハイブリッド勤務を希望しています。
しかし、この「柔軟性への欲求」はニーズとバランスに気をつける必要があります。最近のChannel News Asiaの論説でも指摘されているように、多くの若年層労働者にとって、柔軟性よりも雇用の安定性と明確なキャリア成長の道筋が優先される傾向があります。つまり、FWAは重要な要素ではあるものの、それだけで従業員の期待を満たせるとは言えません。
したがって、FWAはもはや単なる福利厚生の一部ではなく、**包括的な従業員価値提案(EVP:Employer Value Proposition)**の基盤として位置づけられるべきです。雇用主は、FWAを「安定的かつ成長志向のキャリア」の一環として位置づけることで、自社ブランド価値を高め、幅広い地域から優秀な人材を惹きつけ、従業員満足度を向上させ、持続可能な組織運営を実現することができます。
現在、シンガポールでは電子工学、金融、情報通信、運輸、小売業など、91%の業界が何らかのFWAを導入しています。
一方で、柔軟性の提供だけでなく、キャリアの安定性や職業上の安心感を軽視してしまうと、人材獲得競争で後れを取るリスクがあります。企業は以下のような戦略的アプローチを採用することが求められます。
- 柔軟性の常態化: 「特別なもの」ではなく、企業と従業員双方にメリットのある制度として位置づける。
- 成果重視のワークフロー: マネージャーや上司は、「労働時間」ではなく「成果」で評価する考えを身に着ける。
- 生産性の高い職場づくり: 明確な目標設定と期待値を共有し、勤務形態にかかわらず、個々の成果責任と成長を支援する。
- 透明性のあるキャリア開発: 勤務形態に左右されず、すべての従業員に成長機会を提供する。メンター制度、トレーニング、重要プロジェクトの参加などを通じて、全社員が成長できる環境にする。
- スキル投資: 従業員のリスキリングやアップスキリングを積極的に支援し、長期的な雇用維持の姿勢を示すとともに、キャリア定着を強化する。
また、シンガポールの高齢化率は20.7%に達しており、介護などの理由により約26万人の生産年齢層が労働市場から離脱している現状もあります。これは、柔軟な働き方の必要性が今後さらに高まることを示しています。
給与水準を満たすだけでは成功とは言えません。
信頼、柔軟性、ウェルビーイングを組織文化に統合することこそが、未来の競争力を支える鍵です。
今すぐGJCの**「2025年報酬・福利厚生ガイド」**をダウンロードし、人材獲得・定着に向けた実践的戦略とベンチマークデータをご覧ください。https://form.jotform.com/252951037107453
お問い合わせ:https://www.goodjobcreations.jp/services-for-employers/