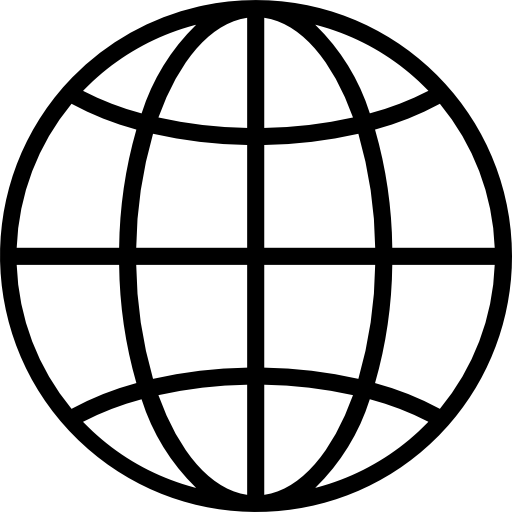執筆者: Gabriel Chua 編集者: Destiny Goh |
グローバル化が深化する現代のビジネス環境において、文化的多様性はもはや単なる流行語ではなく、企業にとって競争優位性を確立するための戦略的要素となっています。弊社グッドジョブクリエーションズ(GJC)は、日本と東南アジア、とりわけシンガポールにおける文化の機微を深く洞察し、それを事業に融合させることで、新たな次元の協働とを切り拓いてまいりました。日本固有の献身的な姿勢とシンガポールの実用を重んじる精神とを組み合わせることで、弊社は文化的な背景の違いを乗り越えるのみならず、むしろそれを事業成功の揺るぎない礎へと転換させております。
シニア営業であるコウタが初めてシンガポールに赴任した際、文化の違いからクライアントとの関わり方を見直す必要に迫られました。顧客を非常に重視する日本の価値観に慣れていた彼は、現地チームの多様な視点に当初戸惑いを覚えました。しかし、シンガポールの同僚たちが、それぞれの多様な文化的背景を活かし、顧客との対等な信頼関係と、期待に基づいて巧みにパートナーシップを築く様子を目の当たりにし、理解が深まりました。日本的な献身性とシンガポール(ローカル)の実用主義の融合により、強固なクライアント関係を築き上げることができるようになりました。これは、多様な文化的インテリジェンスがいかにビジネス成功の鍵となるかを示す良い例です。
このようなストーリーは、私たちGJCで数えきれないほど経験してきたものであり、多様性が単なる企業価値観ではなく、東南アジアにおけるビジネスの成功を推進する戦略的優位性であるということ示しています。
東南アジアに進出する日本企業は、日本と現地のビジネス慣行との間の文化的なギャップという、大きな障壁に直面することがあります。
私のGJCでは十年以上にわたり、この課題を強みに変えるべく取り組んできました。マッキンゼーの2019年の調査では、文化的多様性が高い企業は、低い企業と比較し36%高い収益性を上げていると結論づけています。
私のGJCでのキャリアは十年前に始まりました。2014年にコンサルタントとして入社し、経験を積み 、 2020年にゼネラルマネージャーに昇進しました。経営陣の一員となったことで、多様なチームを構築し、率いる上で避けられない課題に取り組み、その変革力、物事の考え方やその実体験を得ることができました。
日本とシンガポールのメンバーで構成されるチームにおいて、最大の課題はコミュニケーションです。シンガポールでは、職場において直接的な表現が好まれる傾向があります。対照的に、日本のコミュニケーションは一般的に、より間接的で婉曲的です。
例えば、日本の従業員は、対立を避け、職場の「和」を保つために、メッセージの意味が、その状況や互いの関係性によって変化したり、文脈を重視する傾向があります。 これが、それぞれの意図の誤解やボディランゲージの読み間違いといった誤解を生む原因となり得ます。 これらの問題は、しばしば「正しく」または「敬意のある」コミュニケーションに対する見解の違いから生じます。GJCにおける解決策は、「言う」だけでなく「示す」ことです。これは、経営陣やリーダーが業務中にオープンなコミュニケーションや対話を実践することから始まり、それが他のメンバーへと波及効果を生み出します。
ある時、私たちのコンサルタントと営業担当者のチームが、プロジェクトに取り組む中で意見の不一致から大きな問題に直面しました。深く掘り下げた結果、根本原因は期待値のずれと誤解にあることが判明しました。
これを効果的に解決するため、私たちは中立的な第三者、すなわち日本とシンガポール双方の文化のニュアンスを理解し、両者と協働した経験を持つリーダーを任命しました。その結果、提示された代替案を通じて、両当事者は問題を円満に解決することができました。
私たちは中立的な第三者、すなわち日本とシンガポール双方の文化のニュアンスを理解し、両者と協働した経験を持つリーダーを任命しました。その結果、提示された代替案を通じて、両当事者は問題を円満に解決することができました。
人間関係の構築も依然として鍵ですが、ビジネスのペースや問題解決のスピードは日本よりも速い場合があります。日本人は敬意の表れとして時間厳守を重んじますが、シンガポール人は個人の自律性に対してより柔軟な傾向があります。
ある日本人チームメンバーは、日本企業でしばしば実践される社内の非公式な水面下での合意形成プロセス(根回し)に慣れていました。そのため、社内で重要な変更を行う際には、公式な会議の前に気軽な非公式ミーティングを行うことがあります。彼が会社の意思決定の速さに驚いたのは、その”根回し”をすることが少ないためでした。彼は後にこう語っています。「シンガポールのビジネスでは、慎重な計画も重視される一方で、効率性と迅速な意思決定に焦点を当てていることに気づきました」。このより直接的なアプローチに適応することが、ここでの私たちの成功に不可欠でした。
文化への没入は、真の人間関係を築きます。これには、調和のとれた関係を維持するという考え方や、日本のビジネスにおける「お互いの感情や面子(メンツ)」を保つ必要性などが含まれます。文化的な違いにもかかわらず、私たちのメンバーは互いを補完し合っています。
日本人メンバーは細部にこだわり、綿密であることで知られており、シンガポール人メンバーの効率性とスピードによって補完されることが多く、結果として高品質かつ納期通りの成果につながっています。
日本とシンガポールの文化に共通する価値観を共有することは、戦略的に有利な側面を持っています。日本の文化における年長者や経験者への敬意は、意思決定が経験に基づいていることを表しています。一方、シンガポールの文化は、年長者を尊重しつつも、若手チームメンバーが創造的な解決策を提案できるような、よりオープンな対話を促進します。これにより、日本のプロフェッショナルは多様な視点やアジャイルな思考に触れる機会を得られ、同時にシンガポールの若手は経験者よる指導と安定性の恩恵を受けるというダイナミズムが生まれます。最終的には、より強固でバランスの取れた成果につながるのです。
文化的多様性を推進するリーダーは、その本当の力を目の当たりにするでしょう。
そして、その力を感じるためには、組織全体が多様性のもたらす恩恵を理解できるようサポートしなければなりません。人々は(文化や異なるビジネスエチケットなど)何かに関心を持つと、詳細を知りたくなります。GJCでは、仕事における「楽しさ」を重視しており、それが学習を興味深いものにします。多文化チーム間の交流を促進するため、様々な社内イベントによって、メンバーを巻き込んでいます。その一つが、グループランチのアイデアでした。
このカジュアルな場は、メンバーが素直に心からの会話を交わし、文化的なギャップを埋めることを可能にしました。互いをより良く理解することが、意見の相違を解消し、それぞれのニュアンスを受け入れることにオープンになったと語るメンバーもいました。また、この体験をそれぞれが、社内のグループチャットでシェアするようになったのです。
フォーマルな場としては、直属の上司が毎月1対1のミーティングを実施し、メンバーが多文化チームで働く上での学びやフィードバックについて話し合えるようにしています。
1対1で行うことで心理的安全性を高め、共有しやすくなります。 問題が解決しない場合は、マネージャーが解決策を提案する責任を負います 。GJC では、メンバーがトライ&エラーを通じて段階的に学ぶこともサポートしています。
GJCの管理職者たちは、多文化チームを率いるための十分な知識と経験を備えています。私たちは彼らに、双方の文化について教育し、メンバーが異なるビジネスエチケットを理解し、尊重し、取り入れるサポートをすることで、互いが助け合えるチームを作っています。
GJCチームの多様性は、ユニークなセールスポイント(独自の強み)です。これにより、多くの地域およびグローバルクライアントへのサービス提供が可能になりました。私たちは各市場の文化に合わせてアプローチを変化させ、業界理解と文化知識がそれを支えています。
「今日のボーダレスなビジネス界において、文化的多様性を受け入れなければ、ビジネスチャンスは制限され、様々な文化的背景を持つ優秀な人材の獲得とリテンションが困難になります。」
今日のボーダレスなビジネス界において、文化的多様性を受け入れなければ、ビジネスチャンスは大きく制限され、様々な文化的背景を持つ優秀な人材の獲得とリテンションが困難になります。結果として企業は、イノベーションを阻害され、グローバルな競争力が育たないという結果を負うことになります。文化的な認識のずれによって組織構築が失敗することもあります。最近でも、多文化チームがクライアントに提供するHR情報をまとめていた際、他のチームとの進め方について異なる見解が生じました。どちらも妥協しなかった結果、生産性が低下、プロジェクトの遅延につながる事態となりました。
文化的多様性は、今後も従来のマネジメント手法の変革を促すでしょう。リーダーは、より協調的かつ個別最適化されたアプローチ、すなわち模範を示す必要があります。例えば、文化間のバイアスに異議を唱えて文化的なギャップを埋め、多様なチームを管理する際には柔軟性を示すべきです。
従業員が安心して自分の視点を共有できるようなフォーラム(意見交換の場)を設けることで、対話を奨励します。リーダーは意思決定において異なる視点を受け入れるべきです。より多くの選択肢を持つことは、より良い選択を可能にし、計画立案に役立ちます。強固な企業文化は、明確なミッション、ビジョン、コアバリューを重視します。日本の”改善”の考え方は、文化、チームワーク、そして成長を重んじるものです。

ガブリエル・チュア [ゼネラルマネージャー]
2011年より10年以上の人材コンサルティング経験を持つ。消費財・サービス業界における営業およびマーケティング分野の候補者を専門とし、2015年以降、日本人を含む多文化チームにおいて、持続的にリーダーシップ能力の向上を遂げてきた。